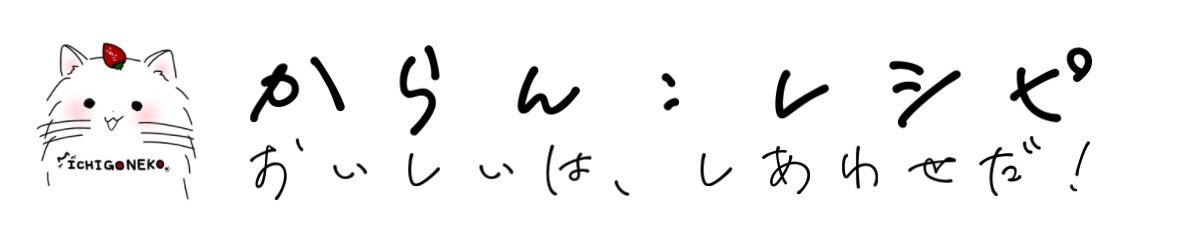こんにちは、からん:です。
最近、ワインをよく飲むようになり、
ワイナリーに行く機会も増えました。
そんな私ですが、
この時期になると耳にする
“ボジョレーヌーボー”
今年のワインが解禁された!
それぐらいの認識です。
今回は、ワインを嗜んでいますと
堂々と言えるようになるためにも
ボジョレーヌーボーについて
少し知識を深めていこうと思います。
ボジョレーヌーボーについて
もう少し詳しくなりたいと思っている方
ぜひ、付き合っていただけると嬉しいです。
ボジョレーヌーボーについて
まず、ボジョレーヌーボーと検索すると、
このような内容がヒットします。
- Beaujolais(ボジョレー地区)
Nouveau(新しいもの) - 11月第3木曜日午前0時に発売
- ブドウは同年に収穫されたガメイ種
(黒ブドウ) - 赤ワイン、ロゼワインのみ
- 醸造方法が異なる
ボジョレーヌーボーが
ボジョレー地区の新酒を指しているのは
名前の意味合いとして理解できるのですが、
ボジョレー地区の新酒はすべて
ボジョレーヌーボーといえるのでしょうか。
発売日の11月第3木曜日は
いったい何で決められているのでしょうか。
なぜ、赤ワインとロゼワインなのでしょうか。
掘り下げていきましょう。
フランスの法律
どうやら、発売日の11月第3木曜日と定めているのは、フランスの法律のようです。
ボジョレーヌーボーは、
フランスの公文書のもとで定義されたワインであり、この規定を守らないとボジョレーヌーボーとは名乗れないようです。
Appellation d’Origine Contrôlée
(フランスの規定書、以下AOC)
いったい、何を守ったら
ボジョレーヌーボーと名乗れるのでしょうか。
AOCの規定内容を掘り下げていきます。
※規定・政令は改定されることがあります
最新の文書を正としてください。
そもそもAOCとは
AOCとは、和訳すると原産地呼称制度となり、
特定の条件を満たした農産物にのみ特定の名称を認める制度です。
AOCでは、
製品名、生産地、分類、生産条件、醸造規則、包装、市場流通、表記、宣言、管理など、
細かい規則が定められています。
定められた条件をすべて満たすことでようやく
認定された原産地名称を名乗ることができるのです。
AOCで規定されているボジョレーヌーボーの条件とは
まず、AOC内に”ボジョレーヌーボー”という
独立した定義は厳密にはありません。
ボジョレー(ボジョレー産ワイン)の規約の中に、
ヌーボー(新酒)をラベルに追加表示する条件として記載されています。
今回は、ボジョレーの中からヌーボーと表記できる条件を、6つに絞って解説していきます。
- 生産量の上限
- 発酵状態の基準
- 不安定要素の計測
- 醸造処理技術の制限
- ブドウの品種
- 市場解禁日
生産量の上限
まず、ヌーボーと名乗れる量に上限があります。
その年のボジョレー産ワインのうち、
ヌーボー(新酒)として申告できるのは最大 42%までと決まっています。
これは、ヌーボーを大量に造ると
、産地全体の品質やブランドが損なわれる。
一部生産者がヌーボー市場だけで過剰に利益を得ないようにする。
このような、品質保持と市場調整のための規定です。
発酵状態の基準
生産期間が短いヌーボーが、
ちゃんと発酵しているかの基準があります。
“瓶詰後の赤ワインは、
発酵性糖分の総量が2g/L以下”
発酵が進むと、ワイン中のグルコースや
フルクトース(=発酵性糖分)が減っていきます。
つまり「どれだけ発酵がどれだけ進んだか」の
指標になるのです。
2 g/L 以下という値は、「発酵がほぼ完了し、
糖分がほとんどアルコールに変わった状態」を示しています。
これは、ワインの安定性と品質を確保するための規定です。
不安定要素の計測
生産期間が短いヌーボーは、
品質の不安定要素が大きいです。
そこで、品質を見極める基準があります。
“未瓶詰のワインは、
揮発酸性の最大許容値が10.2meq/L”
揮発酸性とは、
ワイン中に含まれる酢酸などを指します。
これは、望ましくない発酵によって生成されます。
つまり、揮発酸性が高いということは
「ワインが劣化/微生物汚染がある」可能性が高い
という判断基準になるのです。
10.2 meq/L は、ヌーボーとして許容される
“ぎりぎりの値”として設けられており、
それを超えると欠陥品扱いになることが多いです。
※他の多くのワインでは上限が
8.0~9.0 meq/L 前後に設定されていることが多いです。
醸造処理技術の制限
ワインの製造には、
ワイン成分を濃縮する加工技術があります。
過度の濃縮を禁止し、自然な味を保つ目的で、
この技術の使用量に制限がかけられています。
“赤ワインは、
TSE技術(=ワイン成分を濃縮する加工技術)
の使用上限は最大10%”
ざっくり説明すると、元のぶどう果汁や
ワインの量から水分などを除去して
成分を濃縮する際、元量の90%以下の
体積までしか減らしてはいけないという内容です。
濃縮技術を使いすぎると、
ワインの味わいや香りのバランスが変わり、
原産地の特性(テロワール)を損なう
恐れがあるといった点からも規定されています。
ブドウの品種
ぶどうは同年収穫のものを使用し、
ガメイ種の収穫は原則すべて手摘みです。
機械収穫は認められていません。
これは、マセラシオン・カルボニックと呼ばれる
ヌーボーのために生まれた醸造方法が、
果実に傷がない状態が最良とされるからです。
また、INAOという組織が認可した
収穫時期以前にぶどうを収穫した場合は、
対象外となります。
ボジョレーは赤ワイン中心の産地だったこと、
ヌーボー自体が、赤ワイン早期販売のための
制度として生まれたこと、
マセラシオン・カルボニックが
赤・ロゼ向けの技術のこともあり、
ボジョレーヌーボーは
赤ワイン・ロゼワインのみとなっています。
市場解禁日
1951年に、
ヌーボーの販売が法的に解禁されました。
内容は、その年の収穫後すぐの販売を許可する
という、例外措置のような形のため、
時期に一貫性はありませんでした。
1967年に、市
場解禁日を11月15日に統一されました。
1985年に、
現在の「11月第3木曜日」に変更になりました。
しかし、11月15日が週末に当たると、
流通・販売が難しくなる。
木曜に解禁すれば、
販売店は週末に向けて在庫を準備でき、
金〜日曜にかけて販売のピークを迎えやすい。
このような物流・マーケティングの観点から、
平日の木曜日が最適と判断され、
今もなお11月第3木曜日が市場解禁日となっています。
まとめ
まだほかにも規定はありますが、
このような条件をすべてクリアして初めて
ボジョレー・ヌーボーと表記できるのです。
かなり条件が多く、
ボジョレー地区の新酒というだけでは名乗れないこと、法律により規定されていることが分かりました。
知識が増えると、それだけで
今年のボジョレーヌーボーへの
気持ちが高まりますね。
皆様も、今年のボジョレーヌーボーを
楽しみましょう( ´∀` )
それでは~
ワインに合うお菓子のレシピ